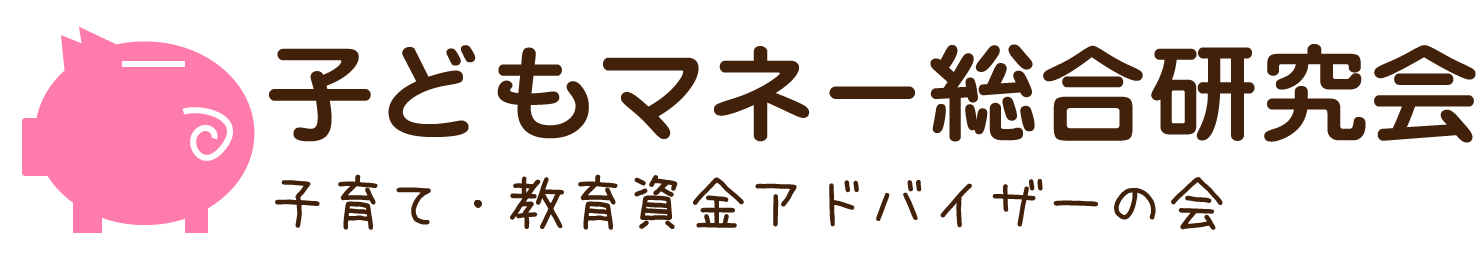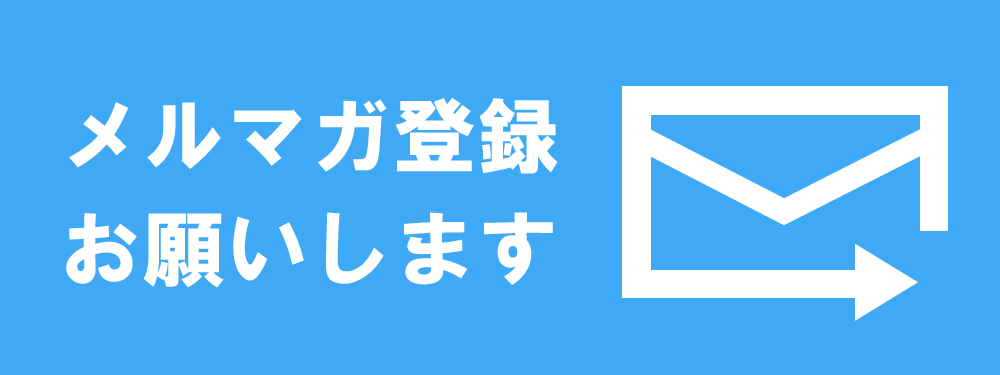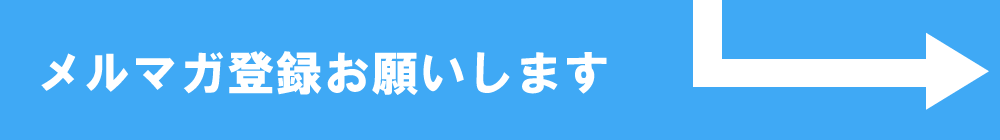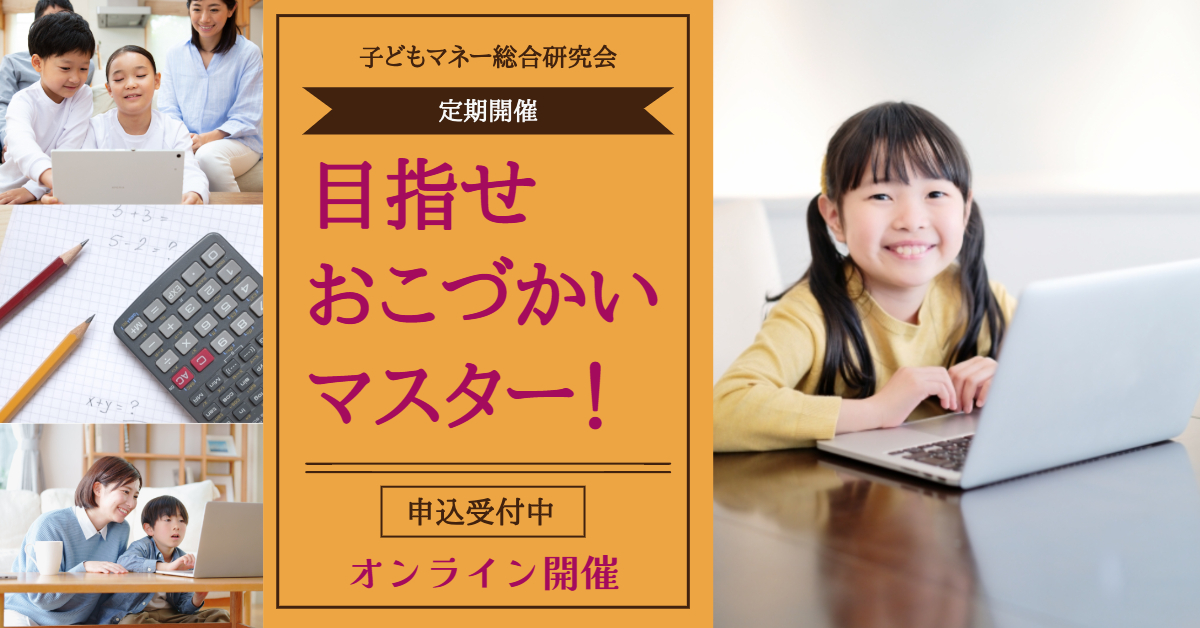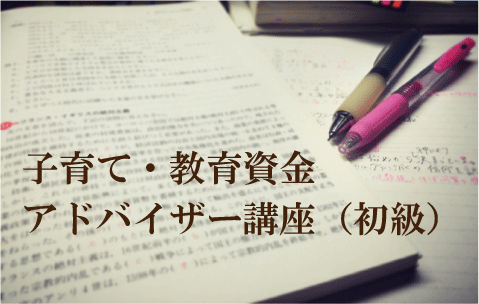妊婦のための支援給付について

妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援と経済的負担軽減を目的に令和4年度から開始された「出産・子育て応援事業」が、子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付」として法制度化され、令和7年4月1日より施行されました。
今回はこちらの制度について確認しておきたいと思います。
令和7年4月1日からの「妊婦のための支援給付事業」とは
妊婦支援給付金は妊婦であることの認定後に5万円、その後妊娠しているこどもの人数の届出を受けた後に妊娠しているこどもの人数×5万円支給されます。
対象者について1回目と2回目で以下の通りとなっています。
1回目の給付 妊娠時
妊婦1人につき、現金5万円を給付
自治体によってはカタログギフトなど選択できる場合もあります。
対象者
令和7年4月1日以降に妊娠届出を提出した妊婦
令和7年3月31日までに妊娠届出を提出した方で「出産応援ギフト」の申請をしていない妊婦
※令和7年3月31日までにご出産された方は、妊婦のための支援給付の対象外となります。
※令和7年3月31日までに妊娠届出をした方で、出産・子育て応援事業の「出産応援ギフト」を申請している場合は対象外です。
※この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義します。
申請方法
妊娠届出の妊婦面談時に配布される申請書に記入、またはWEBで申請など。
2回目の給付 出産時
胎児の人数×現金5万円を給付。
対象者
令和7年4月1日以降に出産した産婦
申請方法
出産後に行う新生児訪問時に配布される申請書に記入、またはWEBで申請など
流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方も支給の対象となります。
妊娠届出前に流産等を経験した方も申請可能です。医師による胎児心拍を確認した際の診断書等が必要となります。
それぞれ支給方法や申請方法などについて、詳しくは住民票のある市区町村の「妊婦のための支援給付」担当窓口にお問い合わせください。
旧制度との変更点は?
旧制度(出産・子育て応援給付金)との相違点についてまとめたものが、こども家庭庁より下記表の通り公表されています。
今回の給付は「妊娠」に着目した「妊婦のための支援給付」と位置付けたことから、給付対象は1回目、2回目とも妊婦となっています。また、2回目の給付においては、妊娠している胎児の数に応じて給付することとし、これまで支給対象外だった流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となっています。
妊婦のための支援給付と出産・子育て応援給付金の相違点
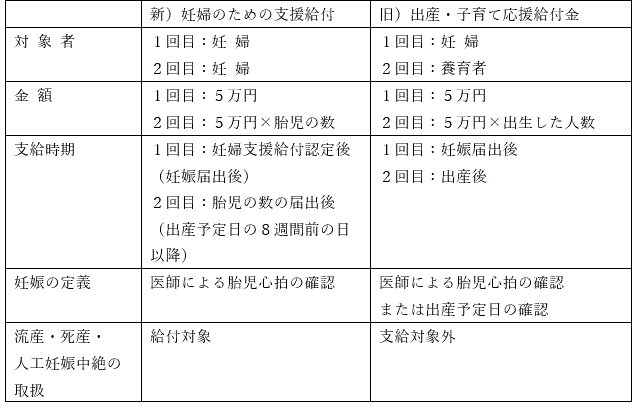
今回の制度では、旧制度でこれまで対象だった方にとっては特に大きな変更はなく、対象外だった方へも支給されるようになった点が大きな変更点となっています。
全ての妊婦に寄り添うことで、妊婦の数を増やし、出生数を増やす方向に進んでいこうということでしょうか。少子化対策の一助となるでしょうか。