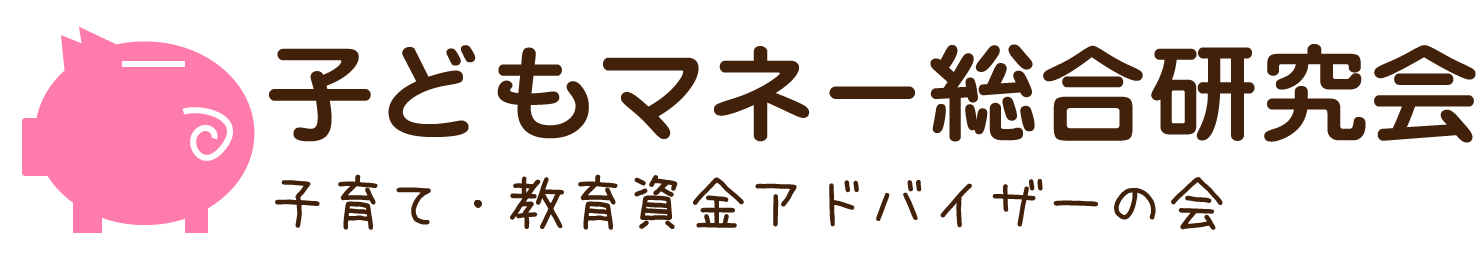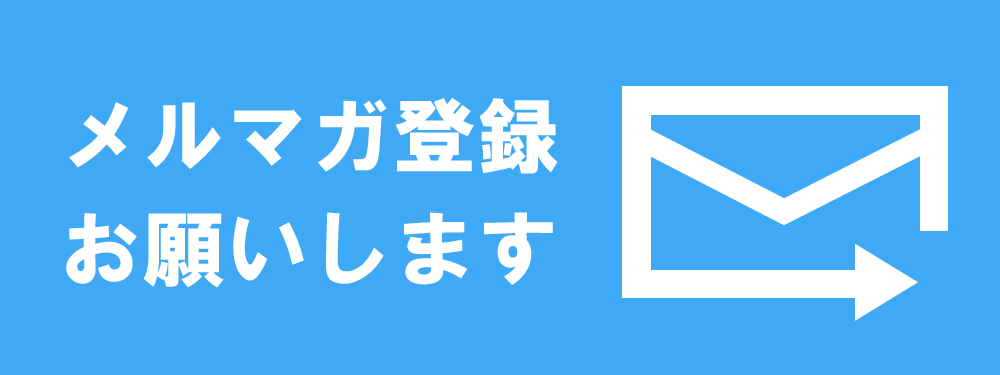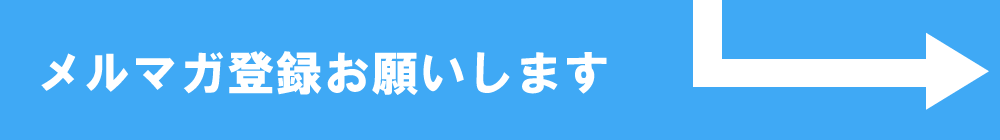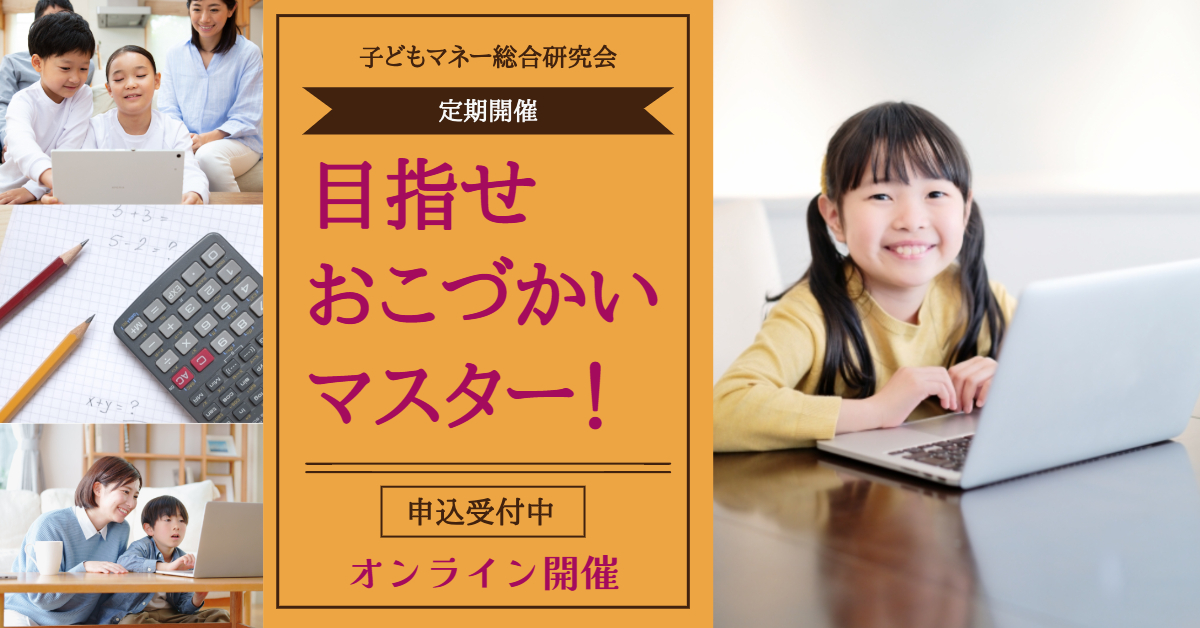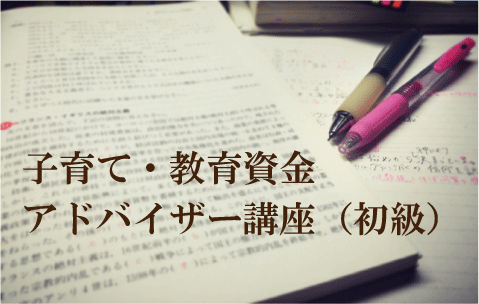子どもたちの夢から始めるキャリア教育とお金の話

「将来、何になりたい?」――この問いに、子どもたちは目を輝かせて答えてくれます。スポーツ選手、パティシエ、先生、YouTuber…。夢は人それぞれですが、その夢の先には「働くこと」や「お金を得ること」がつながっています。
日本の中高生が今、考えていること
2025年ソニー生命「中高生が思い描く将来についての意識調査」では、男子中学生のなりたい職業1位は「公務員」。女子中学生では「芸能人」が1位ですが、「公務員」も上位に入っています。高校生になると、男女ともに「公務員」が1位にランクイン。安定した仕事への関心が高まっている様子がうかがえます。
また、「好きなことを仕事にしたい」「趣味を充実させて生きたい」といった声も多く、夢と現実の間で悩みながらも、自分らしい生き方を模索している様子が伝わってきます。
日本のキャリア教育ってどうなっているの?
日本では、こうした子どもたちの夢を支えるために、キャリア教育が少しずつ広がってきました。
日本のキャリア教育は、1999年の中央教育審議会の答申「初等中等教育と高等教育との接続の改善について」で初めて提唱されました。この答申では、若者のフリーター志向や早期離職の増加などを背景に、学校教育と職業生活の接続に課題があるとされ、小学校段階から発達に応じたキャリア教育の必要性が示されました。
その後、2000年代に入ってからは、文部科学省がキャリア教育の理論的基盤を整え、職業観・勤労観を育むための学習プログラムの枠組みを提示。「人間関係形成能力」「情報活用能力」「将来設計能力」「意思決定能力」の4領域に分けて、各学年で育てるべき能力が明確化されました。
現在では、文部科学省の公式サイトでも「キャリア教育は一人一人の社会的・職業的自立に向けた教育」として位置づけられ、学校現場では進路指導だけでなく、自己理解や社会とのつながりを考える授業が行われています。
お金の話も一緒にしよう
学校で様々な取り組みもなされていますが、ご家庭でもキャリア教育について考えるきっかけはたくさんあります。
たとえば、親自身が働き方やお金への考え方をオープンに話すことは、子どもにとって最高の教材になります。「なぜ今の仕事をしているのか」「どんなときにやりがいを感じるのか」「どんな夢のためにお金を使いたいのか」こうした話を親子ですることで、子どもは「お金の使い方」だけでなく、「お金の稼ぎ方」や「人生の計画」について考えるきっかけになるのではないでしょうか。
夢を応援することが未来への力に
子どもたちの夢は、時代や環境によって変わっていきます。夢を支える情報や教育は、いつの時代も大切です。
家庭や学校で、子どもたちの「なりたい!」という気持ちに寄り添いながら、働くことやお金のことを一緒に考えていく――それが、子どもたちの未来への一番の応援になるのではないでしょうか。
【参考】
・文部科学省「キャリア教育・職業教育の在り方について」
・ソニー生命「中高生が思い描く将来についての意識調査2025」