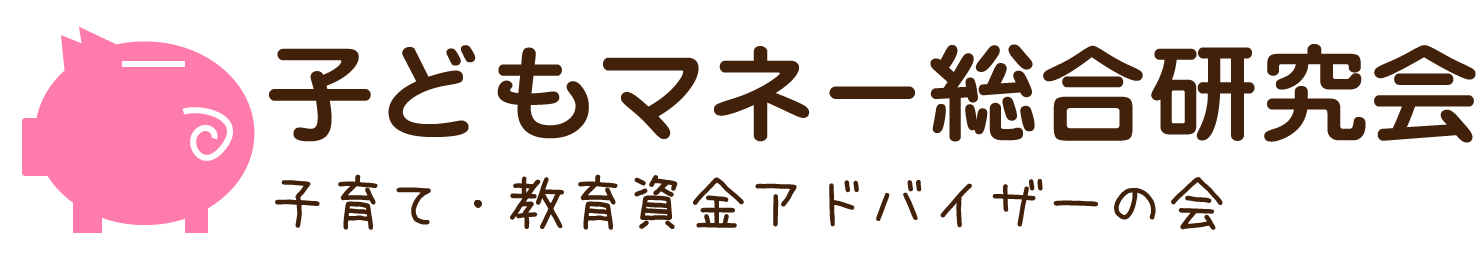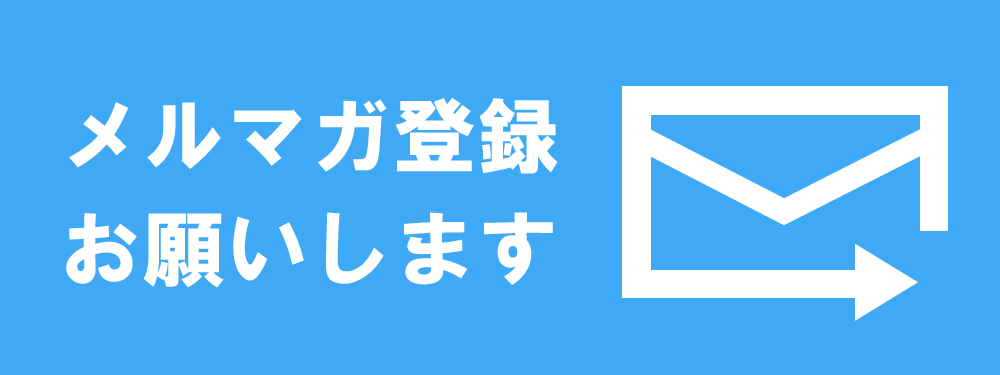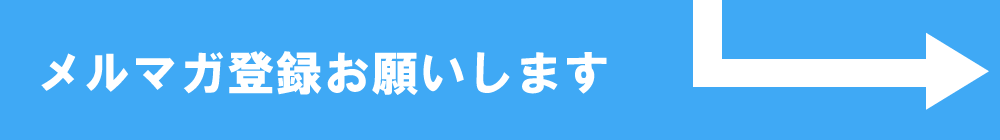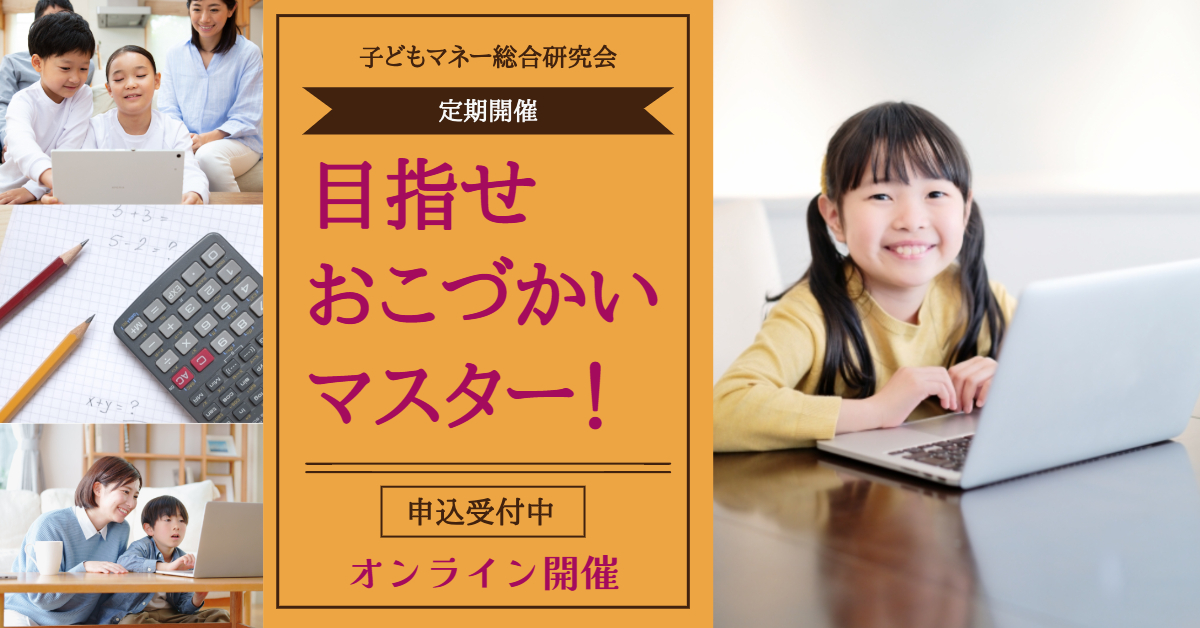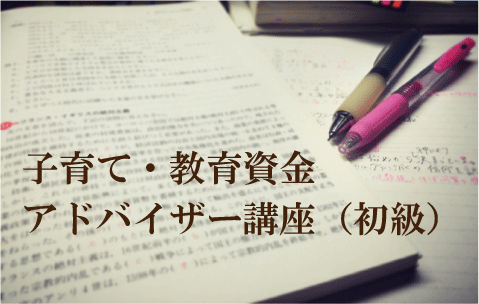仕送り額はどう決める? 大学生等のすまいと生活費

子どもの進路を考えるとき、「自宅通学か自宅外通学か」は、学校選びの大きなポイントになりますね。遠方に進学して下宿等を利用することになれば、家賃や生活費の仕送り費用も進学資金に上乗せされます。保護者は「大学は地元で」のつもりでいても、子どもが「この大学でないと」と言い出したら、遠方への進学を検討する場合もあるでしょう。
今回は、学費に加えて必要になる(かもしれない)「進学資金」である、大学生等への仕送りや住まいの費用について考えてみましょう。
大学生(下宿生)の生活費の平均額は13万円弱、仕送りの平均額は約7万円
まずは、自宅を離れて暮らす大学生の生活費や仕送り額の平均額を確認してみましょう。
全国大学生活協同組合連合会(全国大学生協連)が2024年3月に発表した「第59回学生生活実態調査」によると、下宿生の1か月の生活費(食費、住居費、交通費など)の平均額は127,500円とのこと。そのうち、住居費の平均額は54,130円となっています。
12~13万円の生活費が毎月かかるわけですが、同調査によると仕送り額の平均額は70,120円。生活費と仕送り額の差額分の約57,000円は、奨学金や学生本人のアルバイト収入などでまかなわれているようです。
ただし、生活費13万円弱というのはあくまで平均値。実際には住む場所によって、どんな物件に住むかによってかかる費用は違ってきます。
場所・物件で、すまいの費用には大きな差
たとえば、「東京の大学に進学する」場合でも、23区内か否か、主要駅付近か否かなどで、ひとり暮らし向けのアパートの家賃相場も変わってきます。住まい情報サイトで、地域名を入れてひとり暮らしのアパートを「オススメ順」で検索したところ、それぞれのトップに出たアパートの家賃は下記のようになりました。
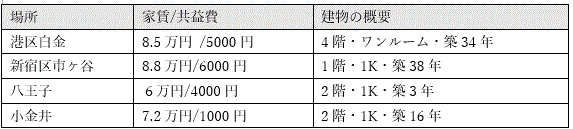
家賃以外の生活費が月額5万円だとすると、家賃が6万円なら生活費は月額11万円、家賃が9万円なら14万円になります。どこに住むかで生活費の額は大きく違い、必要十分な仕送り額も変わってくるでしょう。
このように、進学希望の大学がどこにあるのかわかっていれば、住まい情報サイトなどで、周辺のアパートの相場などを調べられます。検索しながら、住まいに求める条件(オートロック、ユニットバスか否か、クローゼットの有無や広さ、キッチンの仕様、部屋の広さ、築年数、駅までの距離、立地等)をお子さんと話し合っておくと、実際の物件探しのときにも役立ちそうですね。
学生の住まいとしては、家具家電が備え付けで朝夕の食事つきの学生寮や学生会館などもあります。大学併設の学生寮などは月数万円と格安の場合ありますが、学生会館はアパート等よりも高額になる場合もあります。早めに情報を集めておきましょう。
大学等のHPで学生寮の紹介が掲載されていたり、大学生協などのHPで住まいの紹介や周辺地域の家賃相場などが提供されていたりする場合もあります。進学希望先の情報収集と同時に、すまい情報もチェックしてみるとよいでしょう。
「仕送りできる金額」を早めに出して、資金計画を
このように、「大学生等のひとり暮らしの生活費」は地域によって、物件によっても違いがあります。しかし、生活費の額が高いとしても、「我が家の家計」から仕送りに向けられる金額には限度があるはずです。学費のほかに、仕送りにどれくらいの金額が家計で負担できるのかは、早めに割り出しておきましょう。
その上で、「仕送りできるのはこれくらい、生活費にはこれくらいかかるみたい。その差額はどうする?」ということを、早めに家族で話し、資金計画を立てておきましょう。子ども本人が「アルバイトで頑張る」と言っていても、大学等で学びながら働ける時間には限りがあり、思ったようなアルバイト収入が得られない可能性もあります。明らかに不足するなら、奨学金や教育ローン利用の検討も必要でしょう。
また、どんな「すまい」を選ぶかで、かかる費用には差が出ますよね。「この大学の学生寮なら寮費は格安」「古い物件で駅から多少遠くても構わなければ、家賃は抑えられそう」「多少家賃が高くても、オートロックの物件が安心」等、大学等のHPやすまい情報サイトなどを活用して住居費を抑えられる方法はないか、費用がかかっても外せない条件は何かなどを検討するとよいでしょう。子どもがどんな生活をしたいのか、保護者としてどんな生活をしてほしいかを話し合う機会にもなりそうですね。
子どもの進学費用を考えるとき、まず考えるのは学費ですが、仕送り費用も在学中続く、進学費用。「いよいよ受験」という時期になり、調べたり話し合ったりする余裕がなくなる前に、「遠方への進学は選択肢にするのか」「ひとり暮らしするなら仕送りはどれくらいできるのか」「希望進学先での生活費はどれくらいになるのか」を、家族で話し合い、情報を集めて、資金計画を考えておきましょう。