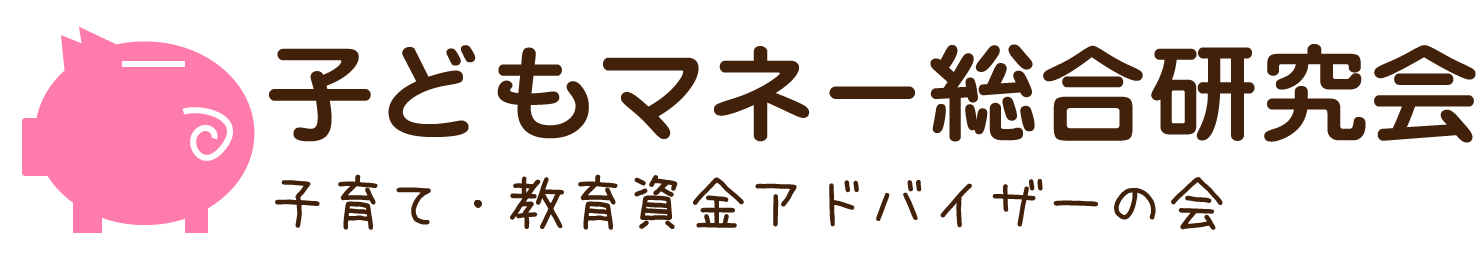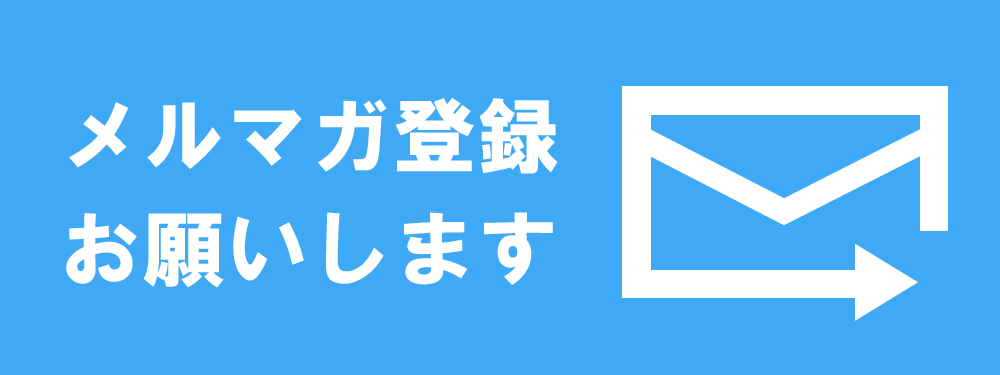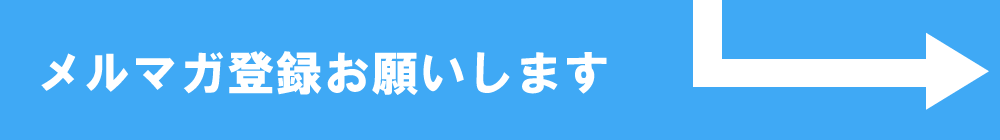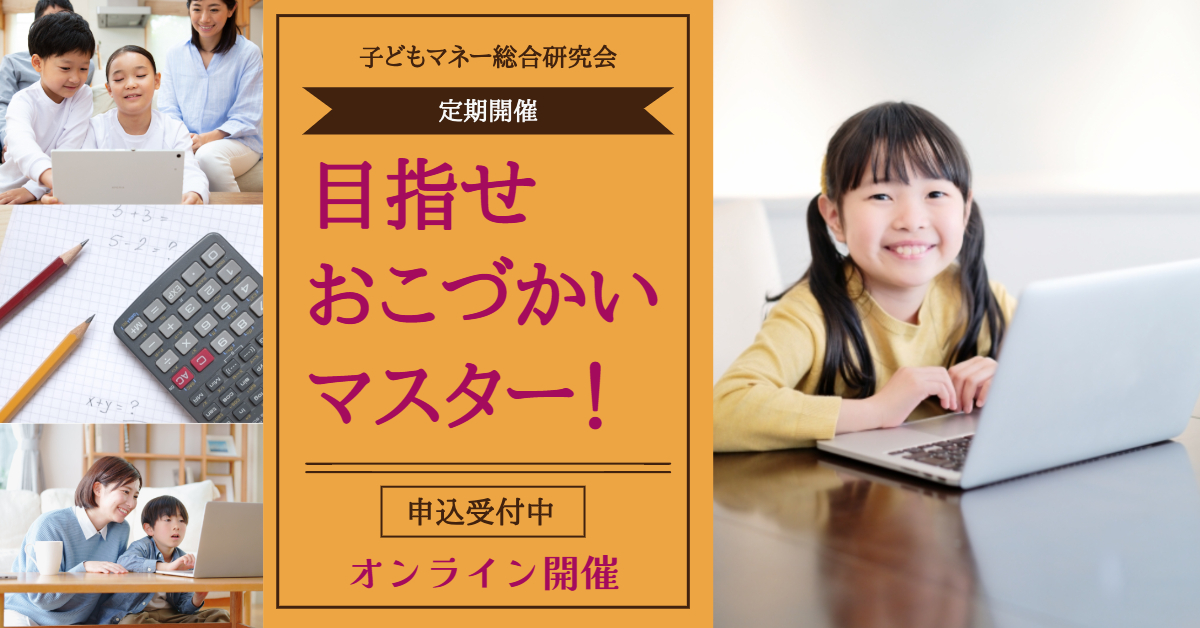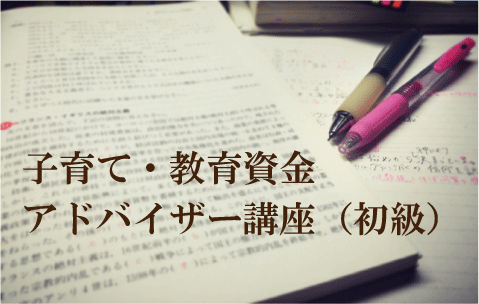学生が意識すべき年収の壁って結局いくら?

2025年から、税制改正の適用により学生の働き方のラインが変更されています。学生がより働きやすくなったと言われますが、所得税、住民税、親の控除、健康保険の負担のうち何を重視するかによって答えは異なります。年末に慌てることがないよう、学生自身も、親御さんも、しっかり押さえておきましょう。
所得税課税のライン「160万円の壁」
大学生など(19~22歳)がアルバイトをする際には、まず、自身の所得税がかかるかどうかのラインを知っておく必要があります。2024年までは「130万円の壁」(103万円+勤労学生控除27万円)として知られてきた所得税がかかり始めるラインが、2025年からは「160万円の壁」に引き上げられました。
引き上げとなった原因は2つあります。給与から引かれる経費に該当する給与所得控除の最低額が55万円→65万円になったことと、課税額を計算する際に引かれる基礎控除の最低額が48万円→95万円(年収200万円以下)となったためです。
所得税がかからないラインとして「160万円の壁」がありますが、学生は、これだけを意識して働くわけにはいきません。
親側の控除63万円が適用される「150万円の壁」
学生の年収が123万円以下であれば「特定扶養親族」となり、親の所得から63万円の扶養控除が受けられます。また、2025年に「特定親族特別控除」が新設されたことで、子の年収が150万円以下であれば、親は「特定扶養親族」に対する扶養控除と同額の63万円の控除を受けられます。子の年収が150万円を超えると、188万円までは控除額が逓減していく仕組みになっています。
世帯での節税効果を考えると、学生はこの「150万円の壁」を意識して働くことが重要となります。
試算をしてみますが、親が63万円の控除を受けることによる節税効果は、親の所得税率が10%なら6.7万円、20%なら12.6万円です。さらに、住民税も含めると、2026年からの特定親族特別控除は45万円のため、所得割が一律10%であることから4.5万円の節税となります。このため、親の所得税率が10%であれば11.2万円、20%であれば17.1万円の節税効果があるといえます。
前述の所得税がかからない「160万円の壁」よりも、親側が63万円の控除を最大限に受けられるラインとして、「150万円の壁」の方が意識されるべきものだと思われます。しかし、他にもが学生アルバイトで気を付けるべきラインがあります。
自分で健康保険に入る「130万円の壁」
学生バイトは、原則、厚生年金には加入しないことになっています。健康保険については、年収が130万円以上になると、職場の健康保険に加入することになります。親の扶養に入っていれば負担する必要がない健康保険料を、自分で支払うことになるのです。会社と折半とはいえ、おおよそ5%弱となる保険料負担は避けたいと考えることでしょう。
そのため、「150万円の壁」以上に、この「130万円の壁」が意識されると考えられます。
住民税がかかる「約110万円の壁」
アルバイトをしている学生から相談を受けたことがありますが、2024年までの「130万円の壁」を意識して働いたところ、所得税はかからないのに、住民税の請求がきたと驚いていました。実際には、所得にかかわらず負担する均等割の年5000円だけだったようですが、それでも想定外だったようです。
住民税は前年の所得に対してかかり、毎年6月頃に住民税決定通知書が届きます。住民税の給与所得控除が10万円アップしたことから、2026年からは通常110万円以下なら住民税がかかりません。ただし、自治体によってこの金額が異なる場合があります。均等割額も同様です。そのため、正確なラインは自治体で確認をしましょう。
自分が働いたアルバイト代から税金を1円も負担したくないという場合は、結局のところ、「150万円の壁」や「130万円の壁」よりも、「約110万円の壁」が重視されそうです。いずれにしても健康保険料の負担は避けたいでしょうから、「130万円の壁」が次のラインとなると考えられそうです。